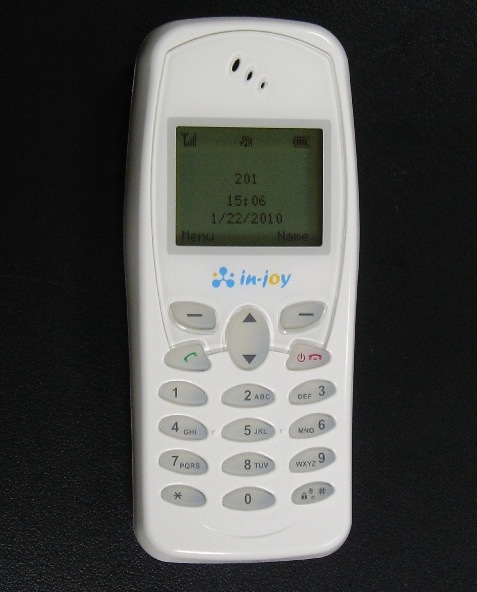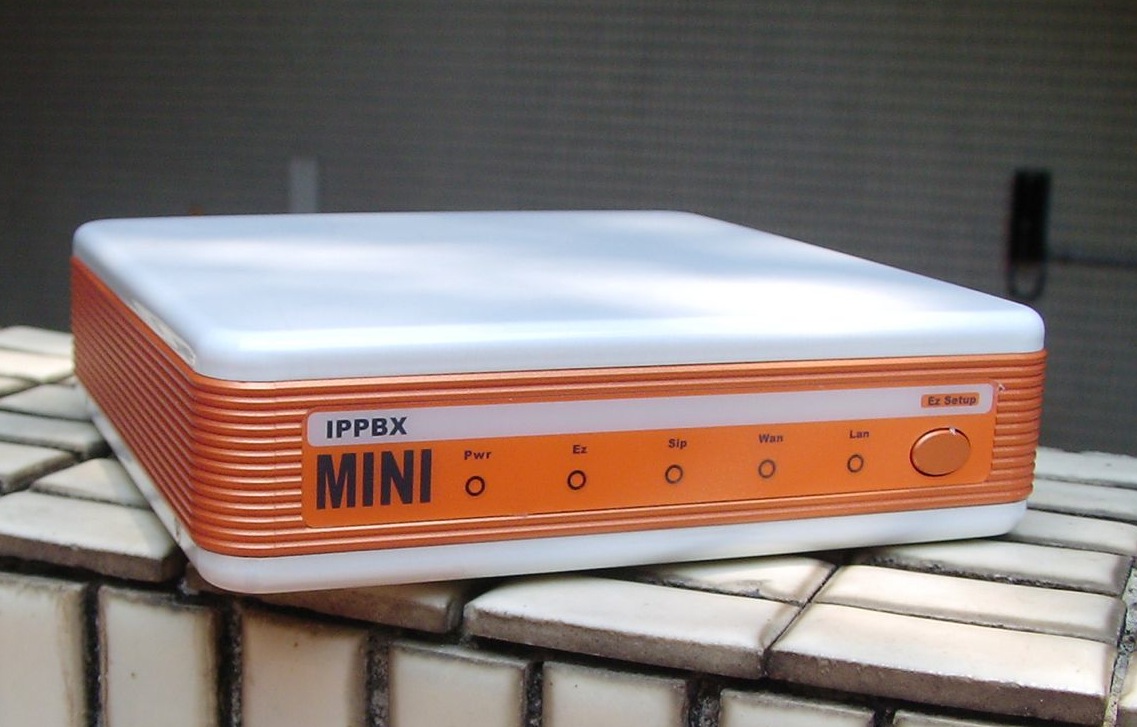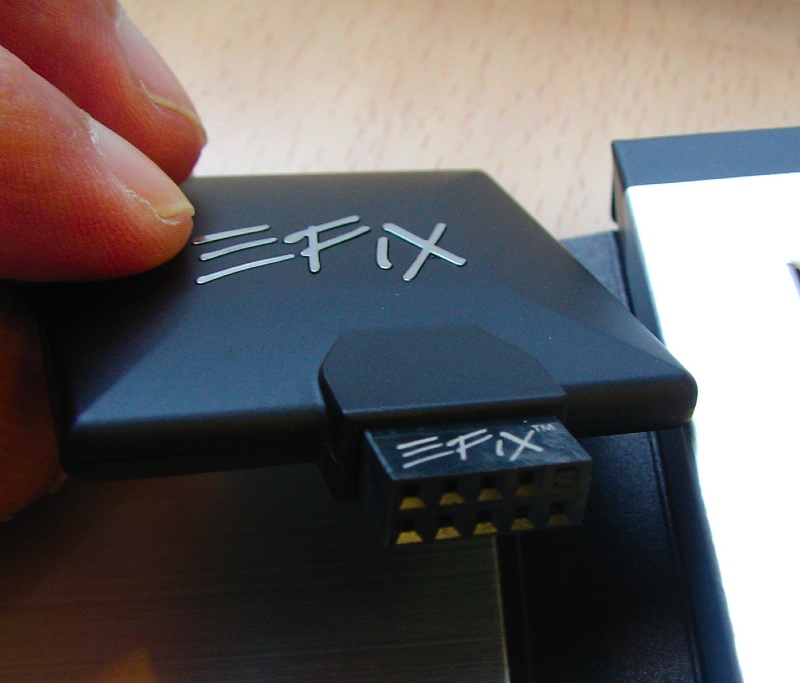商品とサービス
特集
ショッピングカート
カートは空です。
 |
ハイパワーWiFi専門ページ
湯けむり泉遊会
南国台湾楽園生活
悠遊村
AT COM
伝説の名機AT-323の記事
12VOIPのページ
IP PBX UsersのFB Page
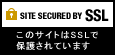
|
ホーム |
CPO日記
CPO日記
CPO日記:70件
無線 IP 電話機を使ってみる
GS-27USBのホンモノ、ニセモノ論議
急激に変わるITSP の勢力地図
ネット上で言論の自由を味わえるツール
MINI100 IP PBX を運用開始して1ヶ月
アスタリスク導入でユビキタスが加速
Computex Taipei 2009
香港のエアポートエクスブレス内のWiFi
時代はデジタルサイネージに
温泉でブログ
話題の山寨機 (中国のノーブランド携帯)
大中華圏のIT用語
デジタルフォトフレーム
台北は桜の季節です。
台湾の消費券
台湾でiPhoneついに発売 - 中華電信から
台湾でもiPhone発売か?
EFiXのノートパソコン版
10月は新製品がラッシュ
Windows PCでMac OSX Leopardを動かす EFiX登場
|